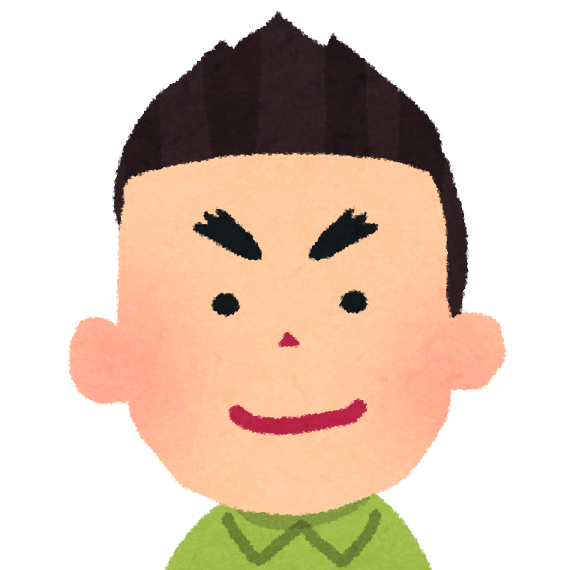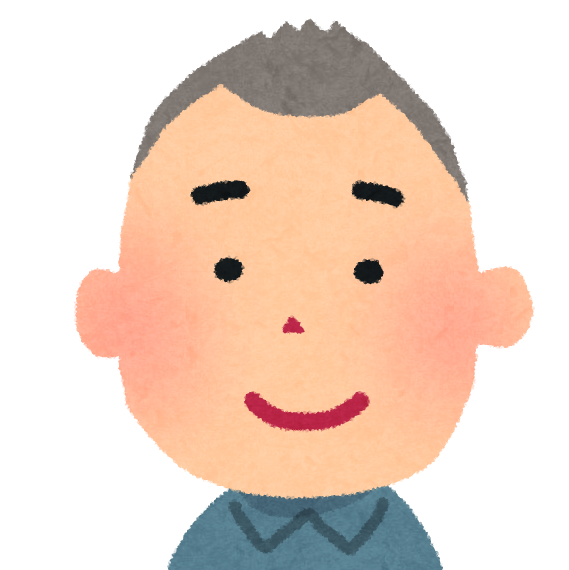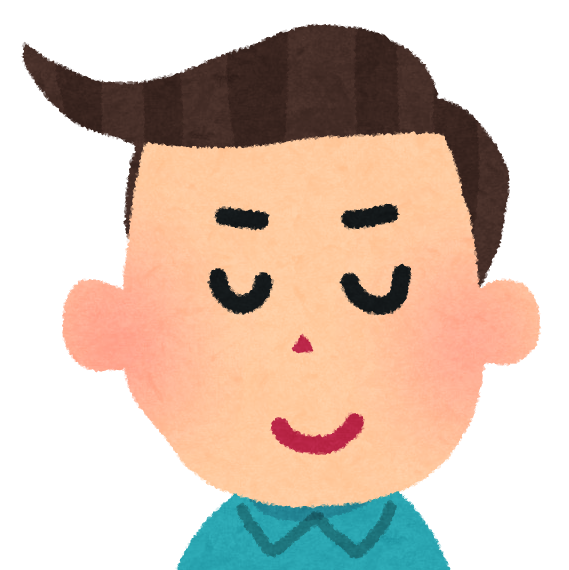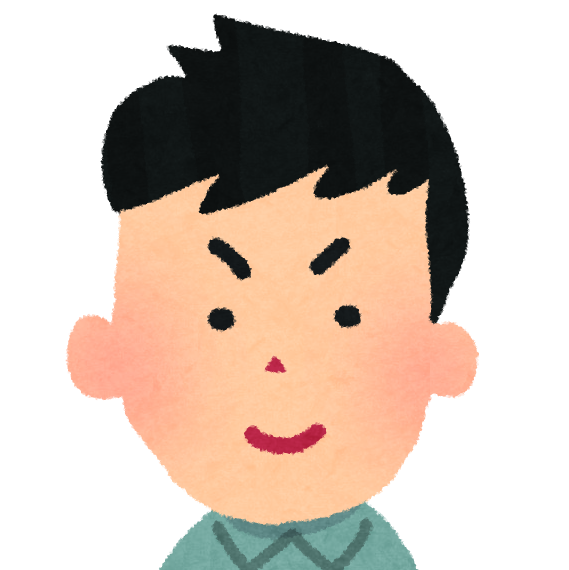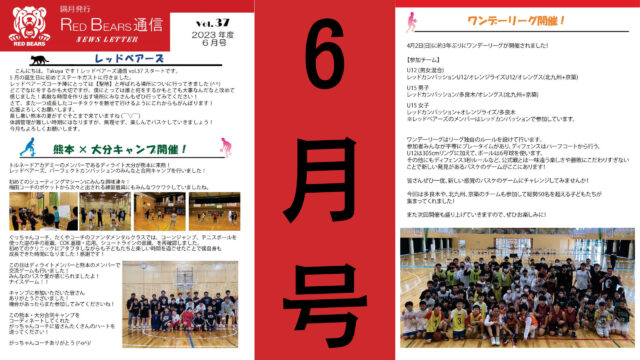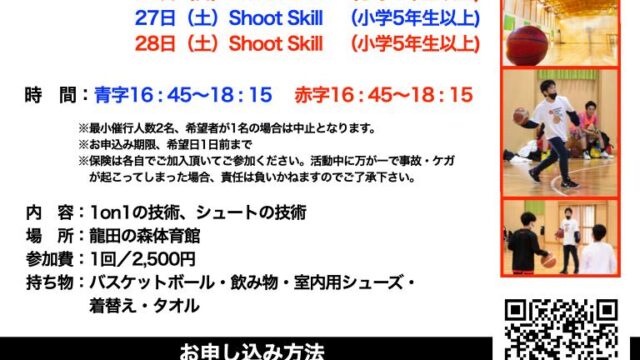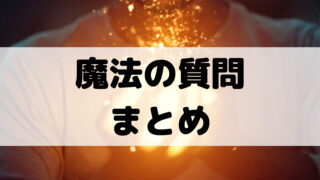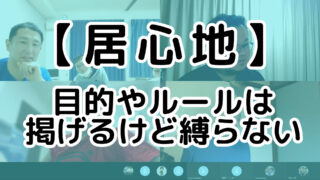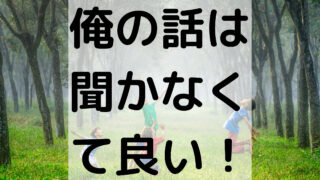【自由とは?】自分が考えてやるときが自由 (トルネードアカデミー代表者会議2023年1月)
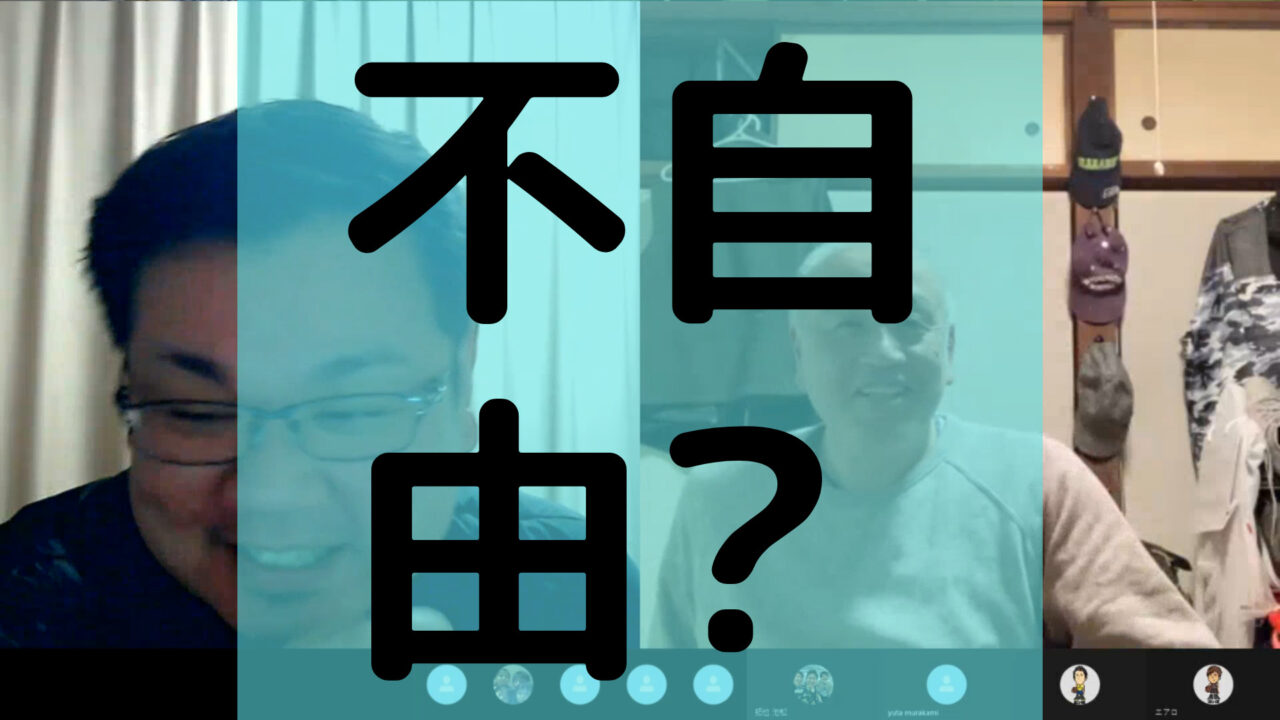
1月のトルネードアカデミー代表者会議の記録です。
未来に繋げるために、少しでも必要な方のお役に立てればと、記録を残します。
2022年度トルネードアカデミーテーマ『FREEDOM』
毎回MTGの初めに1ヶ月でテーマについて向き合ったことを話させてもらいます。
2022年度のテーマ『FREEDOM』について以下の様なことを話しました。
自分が考えてやっているときって自由なんだろうな
不自由に感じていることも、今の不自由の中の自由に満足しているのかもと思ったり、、、
「自習時間に遊んだ」だったり、「掃除の時間にサボった」だったり、ルールを破ったことが「自由」と感じる子どもたちが多かったけど、
大人になっていくと、もっと「不自由」を経験して、「自由」をわかっていくのかなと思いました。
すると、「・・・」となるんですよ。
子どもたちに「自由ってなに?」と聞くと「勝手をしてしまうこと」を言ってしまうみたいですね。
答えを求めるというより、考える時間を与えるという。
「自由」という定義を、国語辞典や英英辞典や世界の人達がまとめてくれてたりするよね。
ウィキペディアとか、、、
定義づけするというのも大事なんだろうなとも思う。「共通認識」するってね。
「自由ってなに?」って聞くと皆がいろいろ言って、「チーム」にはなりにくい。
共通認識するために、言葉に定義づけするというのは、すごく大切なんだなって、58歳にして気づいた。笑
人に言われてやっている時が自由じゃないよね。
難しいよね、でも、そう聞かれたら、みんなだと思う。
僕もこのメンバーでエアロが浮かびました。
熊本工業だよね~?笑
でも、自由ってもっとあるのに、掃除をサボるって、、、なんかかわいいなって。
「わがまま」を言えるようになったら「自由」に向かえてる
私が「良し!」と思う時って、子どもたちが「わがまま」を言ってきた時なんですよね。
その時の「わがまま」が、「自由」に当てはまるのかと考えた時に、自分の中で良くわからなくなったりするから、「わがまま」を言えるようになった選手が「自由」の場に向かえているという風に、考えています。
4人は、それぞれ2人組になってガンガンやってもらうかな。
それぞれのモチベーションでやるかな。
6人いて1人モチベーションが違っても、3・2・2に分かれて、俺が入るようにするかな。
俺の場合、良い意味でも悪い意味でも勢いで持っていっちゃうから、後悔も多いかな、、、人が少ないと寄り添いやすいけどね。
バスケが好きだったら、そのうちやりたくなるのかなぁ、と思うので、その時はそういう気分じゃないんだろうなぁと思います。
その人達のモチベーション、好奇心を一律に見るというよりも、その子は何に興味があるんだろうと、コミュニケーションを取るのが大事なんだろうなと思うな。
モチベーションでいうと、誰かと比べて満足するんじゃなく、自分の中の目標に向かうことで満足するように仕掛けるのが大事だよね。
例えば、3本連続決める!とか。
体験者へのフォロー
熊本ではフォローやアプローチはしてないですね。ただ、定員いっぱいのところに体験や見学に来た子は、定員が空いた時に、入会待ちするしないの連絡が無くても、空きができたことを連絡しています。
すぐに入会する子、入会しない子、返事がない子、いろいろいますね。
兄弟姉妹や、紹介で来られる方が多いので、入会に結びつかないことの方がレアケースですね。
その子に合うイベントがあればMAX6回。大体3回くらいで来る人は来るし、3回返事がない人は縁がないかな。
体験で来た子の保護者さんとどんなことを話す?
僕は「判断する」ということをやりますよ~ということと、「個を認める」ということを伝えています。
個を認めて「褒めて伸ばす」、夢中になった時に仕掛ける、自分を認めると相手を認めていく。コミュニケーションとリーダーシップを最終的にやっていきますと、伝えています。
それを見てもらうといいかなって。次のページからいろいろ詳しくは書いてあるけど。
アメリカインディアンの教え
子供たちはこうして生きかたを学びます
Children Learn What They Live批判ばかり受けて育った子は非難ばかりします
If a child lives with criticism,He learnes to condemn.敵意にみちた中で育った子はだれとでも戦います
If a child lives with hostility,He learnes to fight.ひやかしを受けて育った子ははにかみ屋になります
If a child lives with ridicule,He learnes to be shy.ねたみを受けて育った子はいつも悪いことをしているような気持ちになります
If a child lives with shame,He learnes to feel guilty.心が寛大な人の中で育った子はがまん強くなります
If a child lives with tolerance,He learnes to be patient.はげましを受けて育った子は自信を持ちます
If a child lives with encouragement,He learnes confidence.ほめられる中で育った子はいつも感謝することを知ります
If a child lives with praise,He learnes to appreciate.公明正大な中で育った子は正義心を持ちます
If a child lives with fairness,He learnes justice.思いやりのある中で育った子は信仰心を持ちます
If a child lives with security,He learnes to have faith.人に認めてもらえる中で育った子は自分を大事にします
If a child lives with approval,He learnes to like himself.仲間の愛の中で育った子は世界に愛をみつけます
If a child lives with acceptance and friendship,He learnes to find love in the world.Dorothy Law Nolte
作・ドロシー・ロー・ノルト/訳・吉永 宏
加藤諦三著・アメリカインディアンの教え・扶桑社文庫より
あと、「褒めて伸ばしますよ」「出来なかったことなどに、怒ることは無い」そして、「体験して本人が決めることなんで、本人とよく話して、考えて下さい」と最後には言います。
初めは、なんでこの人は何も言わないのかなと思われるかもしれないけど、子どもたちを見てもらって、納得してくれる人だけが入会してるんだと思います。
後は、スクールの雰囲気を最初に話して、練習が終わったら、必ず、保護者と子どもに話しかけるようにしています。「どうだった~?」とか。「また、いつでもおいでね~」とか。
基本は、入会案内を渡して、それを読んで下さいみたいな感じにはなります。
まとめ
「自由」とは何か?について、深掘りしていく時間となりました。
印象深かったワードは、エアロコーチが言った
「自分が考えてやっているときって自由なんだろうな」
もしかしたら、「自由」を感じれていない子どもたちや、
ルールを破った時に「自由」を感じている子どもたちは、
自分で考えることを、忘れている状態なのかもしれません。
拓也コーチが言った
「自由とは、制限を自分で決めれること!」
なおコーチが言った
「「わがまま」を言えるようになったら「自由」に向かえてる」
これらも、自分で考えたからこその「自由」だと思います。
平和な日本では、「自分で考える」機会が少ないのかもしれません。
平和を作ってくれた大人たちの考えた道を進んでいけば、大きな過ちは起きません。
しかし、自由を感じていない、自由がわからない子どもたちも増えているように思います。
これからの平和を創る大人たちは、「自分で考える」機会を作ることが、必要なのでしょう。
「自由」を考える機会をまずは、大人たちが持つことが、子どもたちの未来に繋がることでしょう。